パナソニックコネクト株式会社では、生成AIを中核としたDXを推進しています。その中心に位置づけられるのが、社内向け生成AIアシスタント「ConnectAI」で、仕事を依頼できるパートナーとして業務変革を牽引しており、幅広い業務シーンで社員を支援しています。2024年度には、全社的な業務時間削を実現しました。
この記事では、パナソニックコネクトが描く生成AI活用のビジョンと、ConnectAIの技術基盤、導入・運用体制、成果、そしてこれから目指すAIとの共創について解説します。
パナソニックコネクトが目指す生成AI活用における目標
生成AI活用を通じたパナソニックコネクトの目標は、以下の3つです。
業務生産性向上
パナソニックコネクトが生成AIの導入で目指すのは、人とAIが補完し合う新たな生産性モデルの確立です。これまで人が手作業で行ってきた定型業務をAIに委ねることで、社員は創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。
また、生成AIは業務プロセスを可視化・改善点の提示といった役割も担っており、再現性の高いワークフローが実現します。ConnectAIのような社内統合型AIは、組織横断での情報共有やナレッジ活用を促進することが可能で、部署間の情報の断絶をなくし、プロジェクト全体のスピードと精度の底上げを目指しています。
社員のAIスキル向上
パナソニックコネクトは、社員一人ひとりのAIリテラシーを向上させ、AIと共に成長できる組織文化を築くことも目標に掲げています。AIを「使う側」から「活かす側」へと意識を転換し、全社員が自律的にAIを業務に活用する状態を理想としています。
生成AIの最大効果を得るには、プロンプト設計やAIの限界を理解することが欠かせません。ConnectAIを通じて、社員が実践的にAIを学びながらスキルを磨くことで、組織全体でAI活用が推進されるでしょう。
シャドーAI利用リスクの軽減
シャドーAIとは、社内業務で外部の生成AIツールを利用する行為で、生成AIの普及により問題視されています。シャドーAIによって、以下のリスクを伴います。
- 機密情報の漏えい
- コンプライアンス違反
- 知的財産の流出
パナソニックコネクトではこの課題を早期に捉えており、安全で統制の取れたAI利用環境を整備することを目指しています。外部ツールに頼らず社内で完結したAI利用によって、機密情報の外部流出リスクを大幅に低減します。
ConnectAIの仕組み
ConnectAIを構成するAI技術は、以下の4つです。
ChatGPT API
ConnectAIの中核を支える技術が、OpenAIの「ChatGPT API」です。パナソニックコネクトはこの言語モデルを活用し、社内業務で活用できる対話型アシスタントを構築しました。同社ではAPIを導入するだけでなく、社内向けに最適化したプロンプト設計を実装しています。
また、ChatGPT APIの出力精度を評価・改善する体制を整え、業務プロセスに合わせた最適化を段階的に実施しています。この取り組みによって、ConnectAIはパナソニックコネクトの業務文脈にパーソナライズされた「実務支援特化型のAI」として機能します。
Azure OpenAI Service
Azure OpenAI Serviceは、マイクロソフトが提供する企業向けサービスです。堅牢なセキュリティ基盤とアクセス制御を持ち、エンタープライズ向けのコンプライアンス要件やデータ保護水準を満たしつつ、高性能な生成AIを業務に活用することが可能です。
パナソニックコネクトはAzure OpenAI Serviceを通じて、機密情報を社外に出さない構成を実現しました。また、Azureのスケーラブルな構成を活用し、利用状況に応じた柔軟なリソース配分も可能です。これにより、社員が安心して生成AIを利用できる環境を整えています。
RAG
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、生成AIの応答に社内外の情報を組み合わせることで、回答の根拠を提示する技術です。パナソニックコネクトはこのRAGを活用し、正確性の高い情報検索基盤を構築しました。
従来の生成AIにおける、回答内容の裏付けが不明瞭になりやすい問題を解消するために、社内ナレッジベースや公式ドキュメントをRAGの検索対象に統合しました。社員がAIに質問すると関連情報を検索し、参照元に基づいた説明を提示するため、回答の再現性と信頼性が飛躍的に向上しています。
さらに、FAQ作成・議事録要約・顧客対応マニュアルの更新など、ナレッジを必要とする業務の効率化も促進します。
Moderation API
生成AIの活用にはハルシネーションのリスクが伴い、不適切な表現や誤情報を誤って生成する危険性があります。そこでOpenAIが提供するModeration APIを導入し、AI出力を多層的に監視・制御するようにしました。
Moderation APIは、AIが生成したテキストをリアルタイムに検査し、以下の情報を自動検出します。
- 不適切な表現
- 差別的言語
- 個人情報の漏えい
出力の記録・分析を行うモニタリング体制が整備されることで、フィルタリングや修正対応の履歴を参考に、モデルやプロンプト設計の改善につなげることも可能です。
ConnectAIの導入・運用に向けて対応した準備
ConnectAIの全社展開にあたり、パナソニックコネクトは以下の準備を導入前に行いました。
生成AI利活用ガイドブックの作成
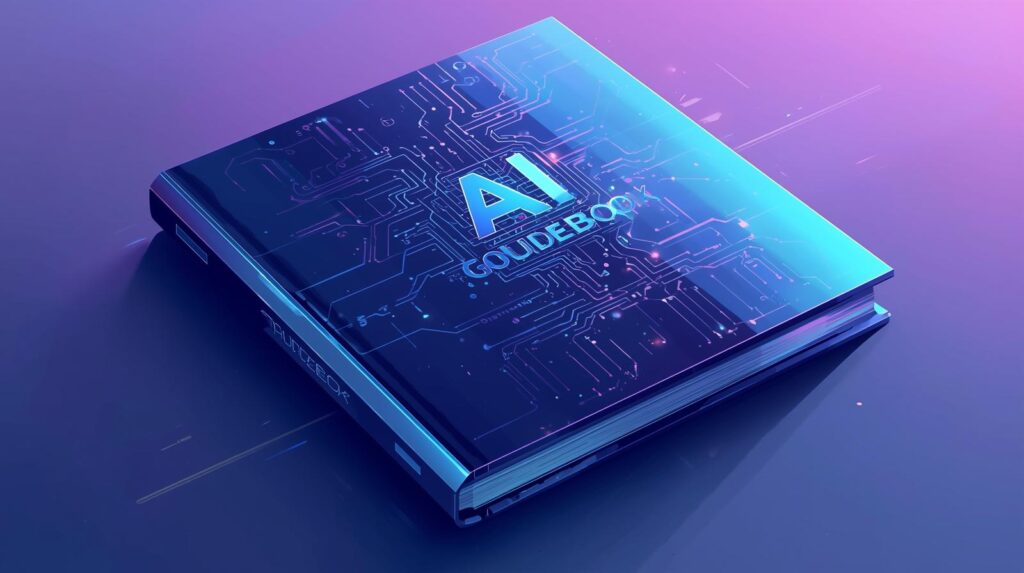
生成AIを全社で安全に活用するために、導入初期から「生成AI利活用ガイドブック」を整備しました。ガイドブックの目的は、社員が安心してConnectAIを利用できる環境を整えると同時に、AI活用の原則と判断基準を明確にすることです。
このガイドブックには、以下の情報が体系的に記載されています。
- 情報漏えい防止や機密データの取り扱い方針
- AIに入力すべきでない情報
- 出力内容の確認プロセス
- プロンプト設計のベストプラクティス
同社はガイドブックを静的なマニュアルではなく、現場の声を反映しながら継続的に更新する「生きたドキュメント」として運用しています。変化の早い生成AI技術にも対応できる体制を維持し、組織全体でAI活用を推進します。
データ利活用支援チームの組織

組織的な運用へと定着させるために組織されたデータ利活用支援チームは、法務・知財・情報セキュリティの部門を連携させています。チームに与えられる役割は、現場部門の要望を吸い上げ、AI活用の成果を最大化するための環境づくりです。
AI技術、情報セキュリティ、業務設計の各領域に精通したメンバーで構成され、ConnectAIの運用方針策定からユースケース支援までを一貫して担っています。また、社員向けにワークショップや勉強会を実施し、プロンプト設計や生成結果の検証手法など、実践的な知識を共有しています。
このように、技術と業務を橋渡しするデータ利活用支援チームの存在によって、パナソニックコネクト全体のAI活用力を底上げします。
セキュリティやコンプライアンスの課題に対しては基盤があり

ConnectAIの導入を円滑に進められた背景には、パナソニックコネクトが元々持っていた「守りのIT基盤」と「統制体制」があります。ConnectAI導入前から、画像処理や個人情報管理といった案件での知見を蓄積しており、AIに求められる倫理性・説明性・安全性に対応する土壌があったとされています。
その既存体制をベースに、以下のセキュリティ技術を組み合わせた多層防御構成を導入しました。
- アクセス権限の分離
- 通信の暗号化
- ログ管理
- アクセス監査
既存のセキュリティガバナンスと技術基盤を活用しながら強化した背景があり、生成AI導入の安全性とスピードの両立を可能にしたと言えます。
「ConnectAI」導入後の効果
ConnectAI導入によって、パナソニックコネクトは以下の効果を挙げました。
年間で約44.8万時間の業務時間を削減
ConnectAIの全社導入によって、年間約44.8万時間もの社内業務時間を削減しました。業務工程を生成AIが支援したことで、情報整理や資料準備に費やしていた時間が大幅に圧縮されました。これは単なる効率化の成果ではなく、業務プロセスそのものを再設計する「知的生産性改革」の結果といえます。
特に、議事録や提案書の下書きといった「繰り返し作業」の自動化による成果が顕著で、社員一人あたりの月間作業負担が軽減されています。また、RAGによって正確な情報検索と要約生成が可能となり、業務スピードと精度の両立も達成しています。
利用方法が「聞く」から「頼む」に変化
ConnectAIの導入によって、パナソニックコネクトでは「AIに質問して答えを得る」という検索的利用から、「AIに仕事を頼む」というスタイルに変化しました。議事録作成や顧客向け資料の初稿作成、要約や翻訳といったタスクをConnectAIに依頼することで、社員は最終調整や意思決定といったより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
また、社内教育やガイドブックを通じて「AIを使いこなす」文化も醸成されつつあり、AIの応答品質を評価・改善提案する仕組みも整備しています。その結果、利用頻度と満足度がともに向上し、社員の思考・行動様式も変わりつつあるようです。
ユニークユーザーの増加・社内活用の拡大
2024年時点で、ConnectAIの月間ユニークユーザー率は49.1%に達し、前年から14.3ポイント上昇しています。利用回数も240万回(前年比約1.7倍)を記録し、社内活用は拡大傾向にあります。
また、法務・経理・ITから現場部門まで特定部門に限られることなく、組織横断での活用が広がったことが報告されています。こうした拡大は、社員が生成AIを業務にどう使うかを模索できる環境の整備が進んでいる結果と言えます。
パナソニックコネクトとConnectAIが目指すAI活用の未来
ConnectAIの導入・活用を全社展開させることで、パナソニックコネクトは以下のロードマップを描いています。
AIエージェントの戦略的活用を加速

パナソニックコネクトはConnectAIをAIアシスタントにとどめず、次世代のAIエージェントへと進化させる構想を打ち出しています。同社が目指すのは「自律的にタスクを遂行するAI」であり、AIが社内システムや業務データと連携し、指示を待たずにタスクを予測・実行できるようになります。
また、社員がAIと共創的に働くための環境整備も進められており、現場主導でエージェントの精度や用途を拡張できる体制を形成しています。ConnectAIは今後、業務における意思決定を補助し、業務変革を先導する戦略的パートナーへ進化していくでしょう。
製造業における品質管理の課題解決に期待
パナソニックコネクトは、ConnectAIを製造業の現場課題、特に品質管理領域に応用されています。製造現場では膨大な検査データや異常検知ログが日々生成されており、それらの情報を活用することが欠かせません。例えば、品質異常の原因分析や是正措置をAIが提示し、担当者が検証・修正することで、判断のスピードと再現性を高めます。
また、製造業全体の品質高度化を目指し、AIを活用したデジタル品質マネジメント(DQM)の構築を進めます。不良要因の早期検知や設計段階でのリスク予測など、現場の判断を支援するAI基盤の実現が期待されていて、品質管理を予測・改善のプロセスへと転換します。
自律的な企業形態「オートノマスエンタープライズ」の実現
パナソニックコネクトが中長期に目指しているのは、AIによる業務が円滑に回る自律型の企業(オートノマスエンタープライズ)です。組織全体が最適化できる構造を目指しており、その中でConnectAIは中心的な役割を果たします。
現時点では、AIエージェントが業務プロセスを先読みし、判断や実行を主体的に進めるというフェーズの実用化が進みつつあります。稟議書ドラフトを起案して自動適に関係部門に回付したり、データ異常を検知したら対応タスクを自動で生成したりといったシステムの導入を目指しています。
このような自律型企業を実現するには、組織文化・監査体制・説明責任といった制度設計が不可欠です。以下のような設計の構築によって、ConnectAIは業務を自律的に動かすAIエージェントへと飛躍し、AIと人間が協働する未来志向の企業に進化します。
- 既存のITガバナンス構造の拡張
- 運用ルールの最適化
- AI判断の透明性を担保する設計
- 説明可能性(Explainability)の確保
社内ナレッジの永続化・民主化
ConnectAIの活用を通じて、パナソニックコネクトは社内に蓄積されたナレッジの永続化と民主化を実現しようとしています。AIが日々の業務で生成・参照する膨大な情報を整理・構造化し、誰でもアクセスできる状態を目指しています。
同社はナレッジの再利用価値を高めるため、AIが業務上のインサイトを自動抽出・整理するシステムを強化しています。これにより、現場で得たノウハウが埋もれず、次のプロジェクトに活かされる循環型の知識基盤が形成されつつあります。
まとめ:AIをアシスタントからエージェントに進化させ、持続可能な社会を実現
パナソニックコネクトのConnectAIは、社内業務の変革と知的生産性の向上を支える中核的なツールへと成長しています。導入初期から安全性と利便性の両立を重視し、AIを安心して使える業務インフラへ昇華させました。その結果、業務時間削減やAIスキルの底上げ、全社的な利用拡大といった成果を生み出しています。
さらに同社は、ConnectAIをアシスタントからエージェントへと進化させ、AIが自律的に判断・実行できるシステムの実現を目指しています。AIがナレッジを蓄積・共有することで、企業全体の知的生産性と持続可能性を高めます。
生成AIの社会実装が加速する今、ConnectAIは人とAIが共創する未来を体現し、持続可能な社会の実現に向かって着実に進んでいます。

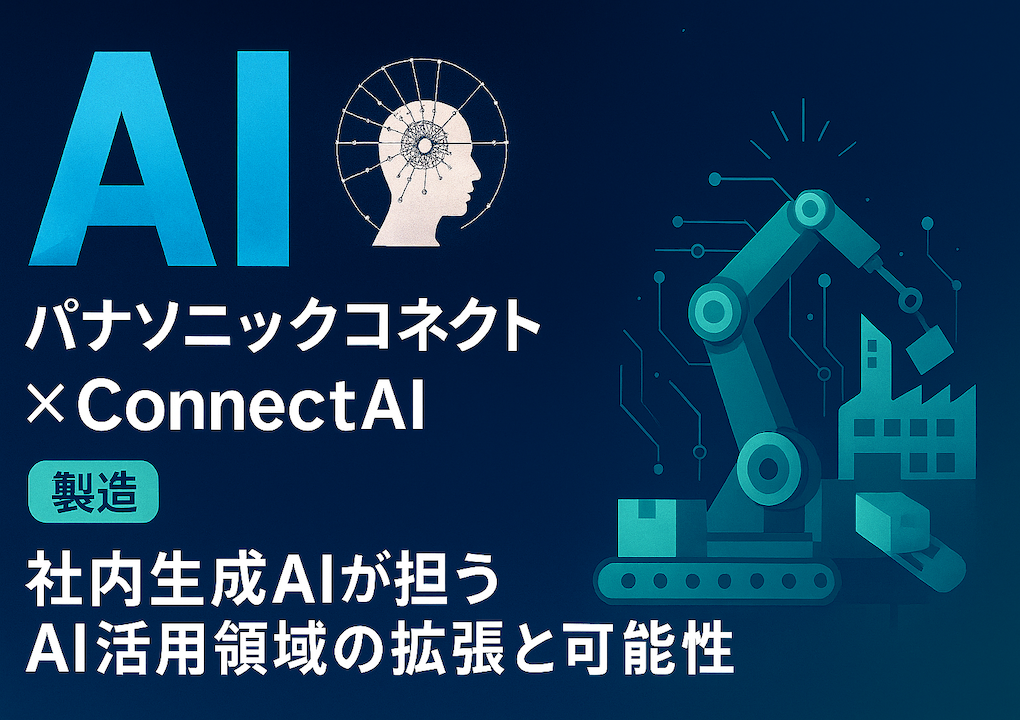
コメント