飲料メーカー大手の株式会社伊藤園は、2023年に特定保健用食品「お~いお茶 カテキン緑茶」のテレビCMにおいて、日本で初めてAIタレントを起用したことで大きな話題となりました。
この取り組みは、単なる話題作りにとどまらず、AI技術の広告分野における新しい可能性を示す事例として注目されています。
このCM実施に至る目的や背景、効果などについて紹介していきます。

画像引用:https://www.itoen.co.jp/news/article/64855/
伊藤園がAIタレントを起用する背景と目的

画像引用:https://www.itoen.co.jp/news/article/64855/
伊藤園の「お~いお茶 カテキン緑茶」にAIタレントが起用されたCMは、現在までに二つの主要なバージョンが放映されており「未来を変えるのは、今!」篇が2023年9月4日から、「食事の脂肪をスルー」篇が2024年4月4日から放送されています。
この背景には、商品コンセプトを効果的に伝えるための最適な表現手段の追求がありました。
商品コンセプトの具現化
CMのテーマである「健康的で明るい未来のために“未来を創るなら今”」を表現するため、「現在の自分」と「素敵な年齢の重ね方をした約30年後の自分」の2つの姿を、別人に見えない同一人物として登場させる必要がありました。
表現上の課題解決
通常のCM制作でこれを実現するには、特殊メイクやCG技術が必要となり、制作上の制約や不自然さが生じる可能性がありました。
AIタレントの活用により、この課題を解決し、自然な形で未来の容姿を表現できると判断されました。
AI技術の活用
伊藤園は、パッケージデザインにも生成AIの技術を既に活用していた経緯があり、広告宣伝においてもAI活用という新たな挑戦を行う土壌がありました。
AIタレントのコンセプト
起用されたAIタレント(AI model株式会社提供の「AI model」)は、見る人の性別によらず、誰もが「健康的」「活動的」「進歩的」「意志の強さ」を感じる人物像として定義・生成されました。
CM制作プロセスと特徴

伊藤園のAIタレントを用いたCM制作は、従来の制作手法とは異なる特徴が見られました。
タレント像の生成と微調整
AI生成で出力された数多くの顔から、商品コンセプトに合致するタレント像を選定。選定後、デザイナーやクリエイターが、「眉毛を1ミリ上げる」「ファンデーションのトーンを調整する」といった非常に細かい微調整を繰り返し、理想のタレント像を完成させました。
タレント像の生成には約2か月を要し、全体の制作期間は従来のCM制作と大きく変わらない時間が必要でした。
これは、初めての取り組みであり、タレント像に徹底的にこだわったためです。
身体の表現
顔だけでなく、体の部分もAIで制作されたのかという問いに対し、詳細な情報は公開されていませんが、AIタレントの動きはまるで本物の人間かのような自然さを持つと評価されています。
声の生成
第二弾のCMでは、声もAI技術で生成され、表現領域がさらに拡張されました。
低コストの実現可能性
有名タレントを起用する場合に比べ、AIタレントは不祥事リスクがない点や、スケジュール調整が不要な点、声優費用を含めても制作コストが抑えられる(数千万円から数百万円程度)可能性があると指摘されています。
ただし、制作期間自体は従来のCMと大きく変わらない場合もあります。
社会的評価と反響

日本初のAIタレントCMは、社会的に大きな注目を集め、様々な反響がありました。
認知度と評価
CMはSNSで瞬く間に拡散され、YouTubeでの再生数も多く記録しました。
ネットユーザーからは「言われないとAIだとわからない」「不祥事リスクがないのは良い」といった肯定的な意見が多く寄せられました。
一方で、一部には「どことなく不気味に感じてしまう」といった意見や、「AIがタレントの仕事を奪うのではないか」という懸念も示されました。
このCMは、VFX-JAPANアワード2024で優秀賞を受賞するなど、技術的な完成度も高く評価されました。
伊藤園のスタンス
伊藤園は、AIタレントは「手段であり目的ではない」というスタンスを強調しています。
起用のメリットとして「自然な形で未来の容姿を表現できる汎用性の高さ」を評価する一方で、デメリットとして「誰もが知る有名タレントではないため、商品や企業イメージを発信する際のインパクトが弱い」点を挙げています。
また、AIで生成したタレントの顔については著作権侵害などのリスクに細心の注意を払い、制作会社から法的見解書を取得するなどして対応しています。
今後のAIタレントの継続的な起用については、企画の目的に合致するかメリット・デメリットを精査した上で検討するとしています。
AIタレントのメリットとリスク:経済的・倫理的な考察

伊藤園の取り組みは、AIタレントが広告分野にもたらすメリットを明確にした一方で、深刻な法的・倫理的なリスクも浮き彫りにしました。
企業にとってのメリット
| 項目 | 詳細 | 補足 |
| ブランド毀損リスクの低減 | 実在のタレントにまつわる不祥事やスキャンダルの心配が一切ない。企業のコンプライアンス順守において、このリスク回避は非常に重要。 | AIタレントはプライベートや出自がないため、イメージダウンのリスクがほぼゼロ。 |
| コストとスケジュールの効率化 | 有名タレントへの巨額なギャラ(出演料)が不要。また、多忙なタレントのスケジュール調整も不要となり、制作工程が円滑に進む。 | 制作期間自体は初挑戦のため従来のCMと変わらなかったが、将来的には効率化の可能性が高い。 |
| 「理想の人物像」の具現化 | 年齢、容姿、雰囲気など、特定のブランドイメージに合致する完璧な人物像をゼロから創造できる。 | 「未来の理想の自分」という難しいコンセプトを自然に表現できた最大の要因。 |
| 表現の汎用性の高さ | 一度AIタレントが生成されれば、あらゆる世代や設定に合わせた姿を生成・展開しやすい。 | CGや特殊メイクよりもはるかに自然で柔軟な表現が可能。 |
法的・倫理的なリスクと伊藤園の対応
| リスク | 懸念点 | 伊藤園の対応 |
| 知的財産権・著作権 | AIが学習した既存の著作物や実在の人物の画像と類似したものが生成され、著作権・肖像権を侵害するリスク。 | 制作会社(AI model社)から、生成されたAIタレントについて、著作権侵害の法的見解書を取得し、リスク回避に努めている。 |
| 労働市場への影響 | AIタレントが広く使われることで、人間の俳優やモデルの仕事が奪われるのではないかという懸念。 | 伊藤園は、AIタレントは「手段であり目的ではない」というスタンスを強調。企画の目的に合致する場合のみ、メリット・デメリットを精査して活用を検討するとしている。 |
| 「不気味の谷」現象 | AI生成の人物が、本物の人間と酷似しているがゆえに、視聴者に漠然とした違和感や不気味さを感じさせるリスク。 | 緻密な微調整とVFXによって高いリアリティを追求し、この現象を回避することに成功したと評価されている。 |
その他のAI活用事例

「お~いお茶 カテキン緑茶」シリーズでは、CM以外にもAIが活用されています。
パッケージデザイン
商品デザイン用の画像生成AIサービス(株式会社プラグの「パッケージデザインAI」)が生成した画像を参考に、人間のデザイナーが最終的に完成させたものが採用されています。
これは、AIをアイデア出しや補助的なツールとして活用し、最終的なクリエイティブは人間の感性で行うという、「生成」ではなく「活用」の姿勢を示しています。
まとめ

伊藤園のAIタレントCMは、製品のメッセージを最も効果的に伝えるための手段としてAI技術を戦略的に活用した日本初の画期的な事例です。
これは、広告業界における新しい制作手法と倫理的な議論を巻き起こし、AIタレントが持つ低リスク・高汎用性といったメリットを社会に示しました。
一方で、AIタレントはあくまで手段であり、企画の目的達成に最適である場合に活用を検討するという伊藤園のスタンスは、今後AI技術をクリエイティブ分野に導入していく上での重要な指針となっています。
今後も、伊藤園がAI技術をどのように活用し、クリエイティブな表現の豊かさを広げていくのか注目されています。

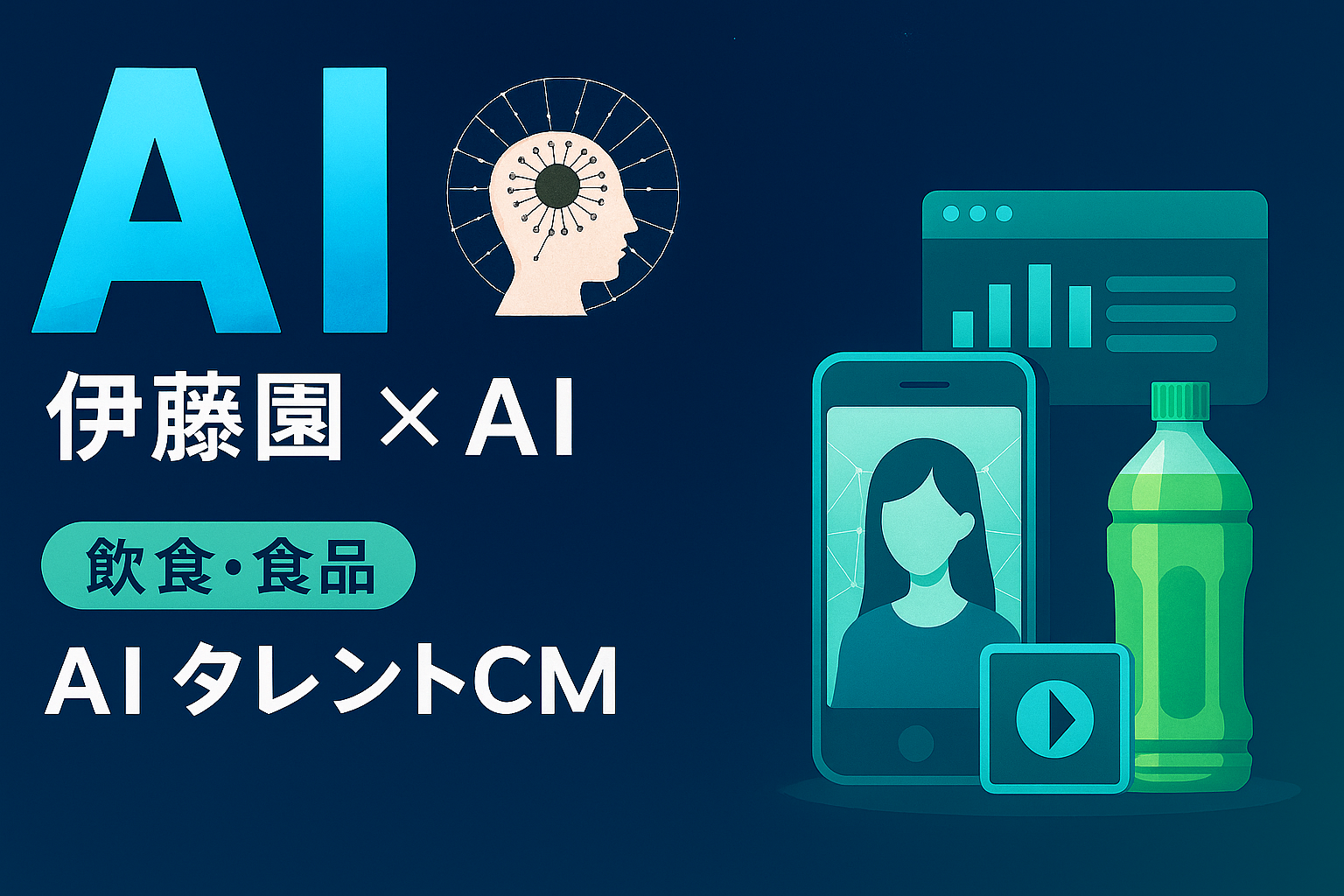
コメント