デジタルデバイスを使用する高齢者も増えてきた昨今、デジタル化と超高齢化社会が加速していく中でAIを使った遺言や遺品の整理が話題となっています。
この記事では、AIを使って遺されるものを整理していくサービスについてご紹介します。
▣デジタル遺品について
現代は、1人につき少なくとも1台のデバイスを持つのが当たり前のデジタル時代です。スマートフォン、タブレット、PCなど、それぞれのデバイスで異なる目的に合わせてデータを管理している人も多いでしょう。それは若い世代のみに限ったことではありません。それらのデバイスは、突然の事故や病気などで持ち主がなくなってしまった際、《デジタル遺品》という形で、家族の手に委ねられます。しかし、パスワードやロック番号などが故人本人にしかわからない場合、処理をするのが大変困難になります。では、デジタル遺品とはどのようなものがあるのでしょうか。総務省の調査における「高齢者におけるデジタル活用の現状」の年齢別スマホやタブレットの利用率と合わせて確認してみましょう。


世代が若くなるにつれて利用率も高くなっており、デバイスの利用が多いほどデジタル遺品の数も多くなると考えられます。
自分のもしもの時に備えての用意、自分の家族が突然不幸に見舞われた時の対処法はどのようなものがあるのでしょうか。
▣デジタル遺品の整理にAIを活用
デジタル遺品を管理するためには、まず手元にあるデジタルデバイス内の個人情報を整理することから始めなければなりません。整理の方法はおおまかに以下(画像1‐1)のような流れになります。

画像の方法では最終的にエンディングノートなどの手書きによるものとなっていますが、AIを活用した管理方法もあります。もしもの時のために生前から活用できるAIツールをご紹介します。画像1‐1の流れの一部としても利用できるため、ぜひ活用されることをおすすめします。
- 写真整理 Googleフォト・PhotoPicker(iOS):AIが写真や動画を自動的に整理。写真整理や写真探しが楽に。
- パスワード管理ツール「LastPass」:複数のアカウントのパスワードを安全に管理。個人向けには無料版が用意されている。
- クラウド型終活ガイドサービス「WeNote」:AIと専門家終活をワンストップでサポートしてくれる。
- デジタル遺言書作成アプリ「Husime.com」:音声入力による自動デジタル遺言書作成。
▣まとめ
今後、各世代でのデジタルデバイスでの利用率がさらに加速していく中で、行政や「地域包括支援センター」などでもスマホ向けのアプリやネットでの情報発信が積極的に取り組まれていることも利用率の上昇につながっています。また、医療や介護のサービスを利用するうえでも、お薬手帳アプリや医療費管理アプリ、PHR(パーソナル・ヘルス・レコード)」アプリが活用されるなどの動向があります。健康データのほかにも、キャッシュレス決済の普及に伴い、資産をデバイスで管理する人も増えています。持ち主の死後、放置されたり、中身がよく分からないまま処分されたりしているスマホが大量にある中で、「遺品スマホを何とかしたい」という需要が喚起されることは想像に難くありません。
生前から、自身のデバイス内のデータを管理し、AIをうまく活用しながら定期的に見直しておくことは、家族が心穏やかに故人を見送る助けにもなるのかもしれません。

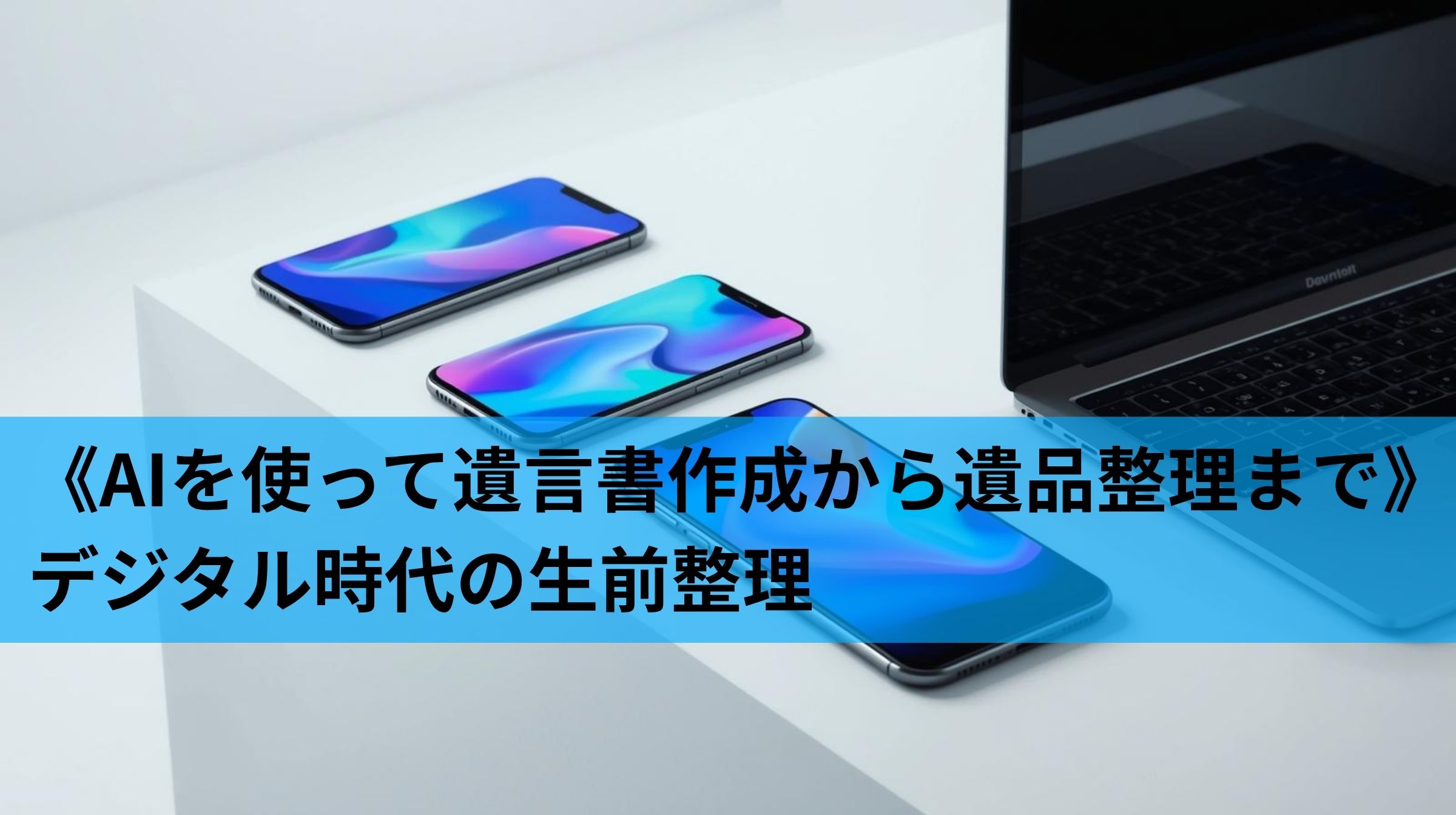
コメント